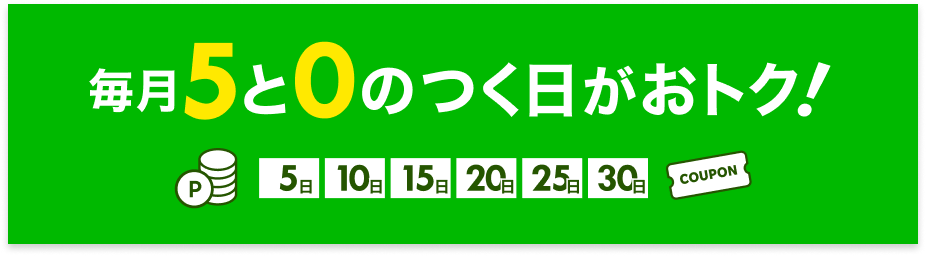8月21日は「噴水の日」
涼しげな水しぶきと心地よい音で、見る人を癒してくれる噴水。
そんな噴水にまつわる記念日が、毎年8月21日に制定されている「噴水の日」です。
一見なんでもない記念日のようですが、実はここに日本の近代化の始まりと、意外な歴史ロマンが隠されているんです。
この記事では、噴水の日の由来や、日本で最も古い噴水、そして高さ日本一の大噴水まで、噴水にまつわるトリビアや観光ネタをたっぷりご紹介します!
なぜ8月21日が「噴水の日」なのか?
その答えは、1877年(明治10年)までさかのぼります。
この日、東京・上野公園で「第1回内国勧業博覧会」が開催されました。
その会場中央に設けられた人工池には、日本初となる西洋式の噴水が設置され、人々を驚かせたといいます。
ただし実際に噴水が完成されたのは9月8日とされていますが、日本における“噴水文化”の幕開けを記念して、博覧会の開幕日である8月21日が「噴水の日」に制定されました。
この博覧会は、日本政府がウィーン万国博覧会(1873年)を参考に開催したもので、推進したのは明治の改革者として知られる大久保利通。
明治政府の「近代化の象徴」としての噴水は、多くの来場者に新時代の到来を印象づけたことでしょう。
実はもっと古い!?兼六園にある“日本最古”の噴水
「噴水の日」の由来は上野公園の噴水ですが、実はもっと古い噴水が日本には存在しています。
それが、石川県金沢市・兼六園にある噴水です。
この噴水は1861年、加賀藩主・前田斉泰によって設置されたもので、なんとポンプなどの機械を使わず、水の高低差だけで動くという構造。
位置エネルギーのみで水を吹き上げるシンプルながらも巧妙な仕組みは、江戸時代の水工技術の高さを今に伝える貴重な遺産でもあります。
長崎や山形にも!個性的な噴水スポット
長崎公園の装飾噴水
長崎市にある長崎公園にも、明治時代から存在する装飾的な噴水があります。
これは、1878年に描かれた「長崎諏訪御社之図」に基づいて復元されたもので、異国情緒あふれる長崎らしい景観が楽しめます。
高さ日本一!月山湖の大噴水(山形県)
そして、日本で最も高くまで水を噴き上げるのが、山形県西川町・月山湖大噴水です。
-
噴水の高さはなんと 112メートル!
-
夜間はライトアップされ、幻想的な光景に
-
季節によって水の打ち上げ方が変化する演出も楽しめる
ダム湖を利用したこの噴水は、圧倒的なスケール感で観光名所にもなっています。
噴水のルーツは古代文明にも!
噴水の歴史は非常に古く、古代メソポタミアやアッシリアの遺跡からも、噴水の原型となる設備が発見されています。
当時から、水は「神聖で豊かさの象徴」とされ、王宮や神殿に水を用いた装飾が施されていました。
西洋においては、ルネサンス期の庭園文化で噴水がさらに進化し、芸術性を帯びるようになります。
現代でも世界各地の都市で、噴水は「美と憩いの象徴」として愛されているのです。
噴水の日に行きたい、おすすめスポットまとめ
「噴水の日」は、明治日本が世界へ開かれた記念日
8月21日の「噴水の日」は、単なる涼感スポットの記念日というだけではありません。
明治政府が世界に開かれ、日本の産業や美意識が進化し始めた“歴史の起点”でもあるといえるのです。
現在の噴水は、涼を感じるオブジェとしてはもちろん、地域のランドマークや観光資源としても大きな役割を果たしています。
この夏はぜひ、お近くの噴水スポットを訪れてみてはいかがでしょうか?
ただの水の柱だと思っていた噴水が、ちょっと違って見えてくるかもしれません。
最近ですと卓上噴水なるものがあるそうです。ただレビューを見る限り多くは海外製で品質に疑問が残るみたいで残念です。

「日本最古の噴水は、ポンプも電気も使ってない!?その秘密は“水の高低差”にあった!」