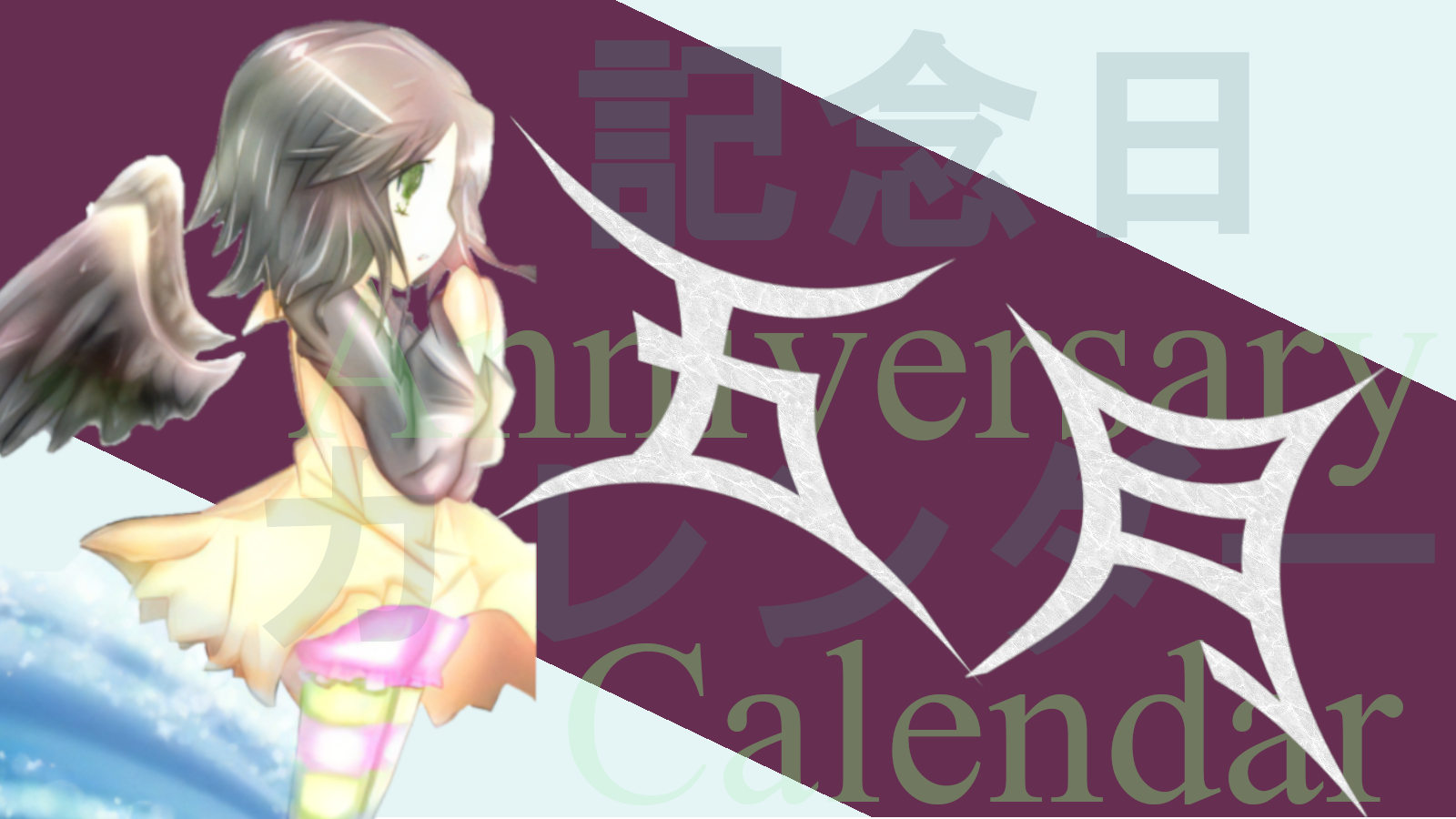5月5日は「端午の節句」
端午の節句とは?いつ祝う?
5月5日は「端午の節句」として、男の子の健康と成長を願う年中行事が行われる日です。この行事は、古代中国の風習が日本に伝わったもので、五節句のひとつに数えられます。
五節句とは、季節の節目を祝い、無病息災や成長を祈る伝統行事で、以下の5つがあります。
端午の節句の由来
端午の節句の起源は、中国・戦国時代に実在した忠臣「屈原(くつげん)」の故事に由来します。屈原は忠誠心の厚い政治家でしたが、国の行く末に絶望して川に身を投じてしまいます。人々は屈原の魂を慰めるため、もち米を葉で包んで川に投げ入れたり、邪気を祓う行事を行うようになりました。これが後に日本に伝わり、男の子の成長を願う節句となりました。
ちなみに「端午」とは、「月の初めの午(うま)の日」を意味し、やがて「5月5日」を指すようになったといわれています。
端午の節句に欠かせない飾り物と意味
五月人形
五月人形には「鎧飾り」や「兜飾り」、「子供大将」などがあり、厄除けや無病息災、立身出世の願いが込められています。武将のように強くたくましく育ってほしいという家族の願いが表れています。
中でも人気なのが、実際に身に着けられる「着用飾り」。子どもに兜を被せて記念写真を撮る家庭も増えています。
鯉のぼり
鯉のぼりは、滝をのぼって龍になるという中国の故事「登竜門」にちなんだもの。逆境に負けず、力強く成長する子になってほしいという願いが込められています。今ではカラフルなデザインやコンパクトタイプも登場し、マンションのベランダでも楽しめるようになりました。
端午の節句に食べる縁起物
柏餅
関東では、柏の葉で包んだ柏餅を食べる風習があります。柏の葉は「新芽が出るまで古い葉が落ちない」ことから、「家系が途絶えない」=子孫繁栄の象徴とされてきました。
ちまき
関西ではちまきを食べることが一般的。もち米を笹の葉などで包み、五色の糸で縛ることで、魔除けや健康祈願の意味が込められています。
また、お祝いの食事として「出世魚(ぶり・はまち)」「たけのこ」「鯛」などを用いた祝膳を用意する家庭も増えています。
初節句でお祝いをもらったら?お返しのマナー
初節句では、祖父母や親戚から五月人形や祝い金をいただくことがあります。その際には感謝の気持ちを込めて、適切なタイミングと方法でお返しをしましょう。
お返しの金額の目安
-
いただいた金額の「3分の1~2分の1」が目安
人気のお返しギフト
-
お菓子の詰め合わせ
-
グルメギフトやカタログギフト
-
タオルやタンブラーなどの実用品
-
お茶・コーヒーなどの飲み物
のし紙は紅白の蝶結びを使い、「御礼」と表書きをして、お子さまの名前を記載するのが一般的です。
お返しのタイミング
-
お祝いをいただいてから「遅くとも1ヶ月以内」
-
お礼状や写真を添えるとより丁寧
まとめ:端午の節句は家族みんなで祝いたい伝統行事
5月5日の「端午の節句」は、男の子の健やかな成長を願う家族にとって大切な行事です。五月人形や鯉のぼり、縁起物の食事など、家庭ごとの工夫で楽しみながら、日本の伝統文化にふれる良い機会になります。

「5月5日は“強くたくましく育て!”の願いを込めた家族の記念日!」