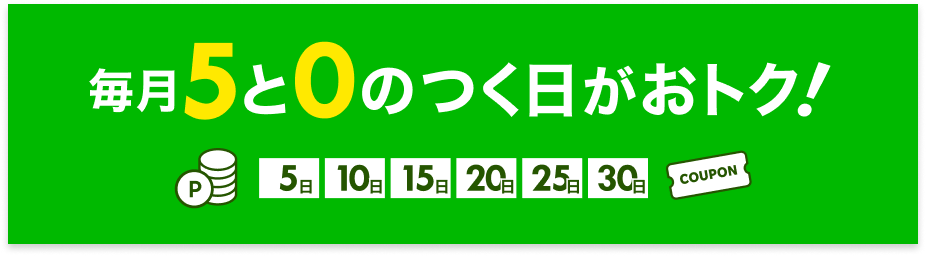毎月24日は「地蔵の縁日」
日本全国の街角で目にする「お地蔵さま」。
実は、毎月24日はこの「地蔵菩薩(じぞうぼさつ)」にご縁のある特別な日、「地蔵の縁日」とされています。
とくに旧暦7月24日(現在では主に8月23日・24日)に行われる「地蔵盆(じぞうぼん)」は月遅れ地蔵盆とも呼ばれ、子どもが主役となる夏の仏教行事として、関西を中心に大切に受け継がれてきました。
この記事では、地蔵の縁日と地蔵盆の意味や歴史、信仰の背景まで、詳しくわかりやすく解説します。
地蔵菩薩とは?“道ばたの仏”が持つ意外な役割
「お地蔵さん」「お地蔵さま」と親しまれる地蔵菩薩。
仏教においては、人々の苦しみを救う“菩薩”のひとりであり、正式にはサンスクリット語で「クシティ・ガルバ(大地の胎内)」といいます。
特徴は、なんといってもその包容力と慈悲。
六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天)すべての世界をめぐり、苦しむ者を救済する使命をもつ仏さまとして信仰されています。
とくに有名なのが、6体のお地蔵さまが並ぶ「六地蔵」像。これは、それぞれが六道の一つを担当しているという教えによるもので、すべての魂に手を差し伸べる存在であることを表しています。
地蔵は“子どもの守り神”としても信仰されてきた
現在、地蔵菩薩は特に子どもの守り神としての信仰が厚く、全国の祠や街角で、子どもの無事を願う親たちによって日々手を合わせられています。
その信仰の背景にあるのが、有名な「賽の河原(さいのかわら)」の伝説。
早世した子どもたちは、親の供養のために河原で石を積むが、鬼に壊されてしまう。それを見た地蔵菩薩が現れ、子どもたちを抱きしめて救う。
こうした逸話から、地蔵菩薩は子どもたちを地獄からも救い上げる存在として深く信仰されるようになりました。
地蔵盆とは?子どもたちが主役の夏の仏教行事
地蔵盆(じぞうぼん)は、地蔵菩薩のご加護に感謝し、地域の子どもたちの健やかな成長を祈る行事です。
主に関西地方(京都・大阪・奈良など)で盛んで、毎年8月23日〜24日にかけて行われることが多く、地域によっては旧暦のままの7月24日に実施することもあります。
地蔵盆の主な内容
-
地蔵堂や祠の掃除・飾り付け
-
提灯やのぼり、花・お菓子のお供え
-
子どもたちによる読経・お参り
-
地域の集会や紙芝居・ゲーム大会など
お寺が主催する場合もあれば、町内会や自治会が中心となって開催する地域密着型の行事でもあります。
お盆明けの時期に、地域の絆を再確認し、子どもの健やかな成長を願う“あたたかな夏の風物詩”として受け継がれているのです。
地蔵信仰はいつから?歴史と全国の有名寺院
地蔵菩薩への信仰は、鎌倉時代から室町時代にかけて広まり、江戸時代には庶民の間に広く根付いたとされています。
全国には「地蔵さま」で有名な寺院も多く存在します。
主な名所
-
【東京】高岩寺(巣鴨):「とげぬき地蔵」で有名。病気平癒・無病息災に霊験あり。
-
【大阪】常光寺(八尾):「八尾地蔵」と呼ばれ、地蔵盆の行事が盛大に行われる。
-
【京都】壬生寺(壬生地蔵):厄除けと子ども守りの信仰が集まる古刹。
-
【奈良】法隆寺、東大寺など:六地蔵信仰の名残が色濃く残る。
地蔵の縁日とは?毎月24日はお地蔵さまの功徳日
「地蔵の縁日」とは、地蔵菩薩と特に深いご縁がある日として、毎月24日に定められています。
この日に手を合わせることで、より深いご加護が得られるとされ、全国の寺院では供養や法要が営まれます。
また、1月24日は「初地蔵」、12月24日は「納めの地蔵」とされ、年始と年末の節目としても大切にされています。
地蔵菩薩のご真言とは?
お地蔵さまに手を合わせるときに唱えるご真言(マントラ)
オン カカカ ビサンマエイ ソワカ
といいます。「オン」は「帰命、供養」。「カ」とはお地蔵様の事である。「ビサンマエイ」は、「類いまれな尊いお方」を表しており、「ソワカ」は神聖な言葉の締めにつけて、その言霊の完成を願います。
このご真言は、地蔵菩薩に直接願いを届けるための言葉とされており、祈願や供養の際に心を込めて唱えられます。
お地蔵さまに願いを込めて、心穏やかに日々を生きる
毎月24日は、お地蔵さまとのご縁を感じる一日。
特に8月の地蔵盆は、地域のつながりと子どもたちの無事を願う、日本ならではのあたたかい信仰文化です。
普段、何気なく通り過ぎていた街角のお地蔵さまに、今日はそっと手を合わせてみてはいかがでしょうか。

「お地蔵さまは、子どもも地獄も、すべて救う“道ばたの菩薩”です。」